2025.8.12
毎年の大雨で雨漏りリスクが高まる!5つのチェックポイント
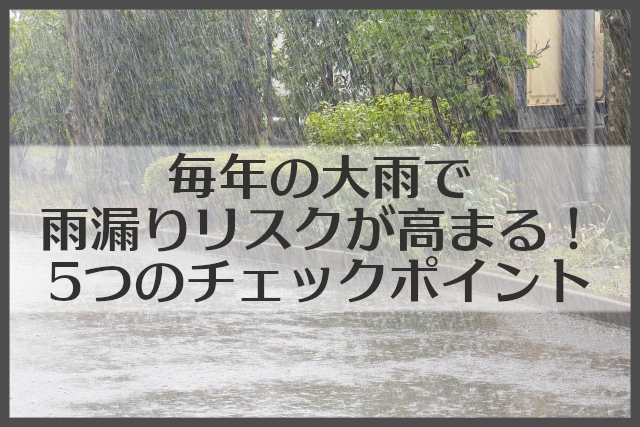
近年、毎年のようにニュースで取り上げられる「線状降水帯」や「ゲリラ豪雨」といった大雨は、私たちの生活にさまざまな被害をもたらします。
その中でも特に注意したいのが、住宅の雨漏りです。
「うちは築年数が浅いから大丈夫」「以前に修理したから安心」と思っていても、集中豪雨の脅威は屋根や外壁、そしてベランダなど、家のあらゆる部分にダメージを与えます。
一度でも雨漏りが発生すると、建物の構造材が腐食したり、カビが繁殖したりと、深刻な問題に発展する可能性があります。
そこで今回は、毎年のように降り続く大雨によって高まる雨漏りのリスクに備えるため、ご自宅の雨漏り対策として確認すべき5つのチェックポイントを解説します。
大雨による雨漏りの原因とは?

雨漏りは、屋根や外壁の劣化が主な原因です。
経年劣化によって防水機能が低下した部分に大量の雨水が流れ込むことで、建物内部にまで水が浸入してしまいます。
特に、近年増加している集中豪雨は、短時間で大量の雨が降るため、通常では問題にならないようなわずかな隙間からも水が入り込みやすくなります。
また、屋根の瓦やスレートがずれたり、ヒビが入ったりすることも雨漏りの原因となります。
外壁のひび割れや、窓枠のコーキングの劣化も同様です。
屋根や外壁は普段なかなか見えない場所だからこそ、劣化に気づきにくいという特徴があります。
大雨による雨漏りを防ぐための5つのチェックポイント

1.屋根のチェック:大雨に備えたい雨漏り対策の基本
屋根は雨漏りの原因で最も多い箇所です。
まず確認すべきは、瓦やスレートのずれ、ひび割れ、欠けがないかです。
屋根材が少しでもずれていると、その隙間から雨水が浸入する可能性があります。
また、屋根と屋根の接合部である棟板金(むねばんきん)の浮きや、錆び、釘の抜け落ちがないかもチェックしましょう。
これらの劣化は、台風などの強風によって屋根材が飛んでいってしまう原因にもなります。
自分で屋根に上って確認するのは危険なので、地上から双眼鏡などを使って確認するか、専門の業者に点検を依頼することをおすすめします。
特に築10年以上経過している場合は、一度専門家に見てもらうと安心です。
2.外壁のチェック:大雨による雨漏りは壁から起こることも
「雨漏りは屋根から」というイメージが強いですが、外壁のひび割れから雨水が浸入し、建物内部で雨漏りが発生するケースも少なくありません。
外壁をよく見て、幅0.3mm以上のひび割れがないか確認しましょう。
小さなひび割れでも、雨水が繰り返し染み込むことで徐々に内部へと水が侵入し、構造材を腐食させる原因となります。
特に、窓やドアの周りのコーキングが剥がれたり、ひび割れたりしている場合は要注意です。
コーキングは、外壁の隙間を埋めて雨水の浸入を防ぐ重要な役割を担っています。
3.ベランダ・バルコニーのチェック:大雨の後の雨漏りを見逃さない
ベランダやバルコニーも雨水が溜まりやすい場所です。
特に排水溝にゴミや落ち葉が溜まっていると、水がうまく流れず、防水層に負担がかかり、雨漏りの原因となります。
排水溝を定期的に掃除し、水の流れを良くしておくことが大切です。
また、ベランダの床面のひび割れや防水層の膨れ、シートの剥がれがないかも確認しましょう。
これらの劣化は、大雨の際に大量の雨水が浸入するきっかけとなります。
4.窓やサッシのチェック:大雨が降ると雨漏りが発生する場所
窓やサッシの周りも、雨漏りが発生しやすい箇所です。
特に、サッシと外壁の隙間を埋めるコーキングの劣化に注意しましょう。
コーキングが剥がれていたり、ひび割れていたりすると、そこから雨水が建物内部へと浸入する可能性があります。
また、窓枠の下側にある水切り部分が曲がっていないか、水切り板と外壁の間に隙間ができていないかもチェックポイントです。
窓から雨が吹き込む場合は、窓枠の劣化や歪みも考えられます。
5.室内天井のチェック:大雨が降った後の雨漏りサイン
大雨が降った後、もし室内の天井に染みができていたり、壁紙が剥がれたりしている場合は、すでに雨漏りが発生している可能性が高いです。
雨漏りの初期症状として、天井からポタポタと水が垂れてくるだけでなく、天井のクロスの変色や、部分的なたるみ、壁に触れたときの湿り気など、さまざまなサインがあります。
これらのサインを見つけたら、すぐに専門の業者に相談しましょう。
毎年の大雨で雨漏りリスクが高まる!5つのチェックポイント まとめ

一度でも雨漏りが発生すると、建物の資産価値が低下するだけでなく、シロアリの発生やカビの繁殖など、住環境にも悪影響を及ぼします。
毎年のように強くなる大雨に備え、定期的にご自宅のチェックを行うことが大切です。
少しでも不安な箇所がある場合は、専門の業者に点検を依頼し、早めの対策を講じましょう。
早期発見・早期対策が、家を守る何よりの防御策となります。













